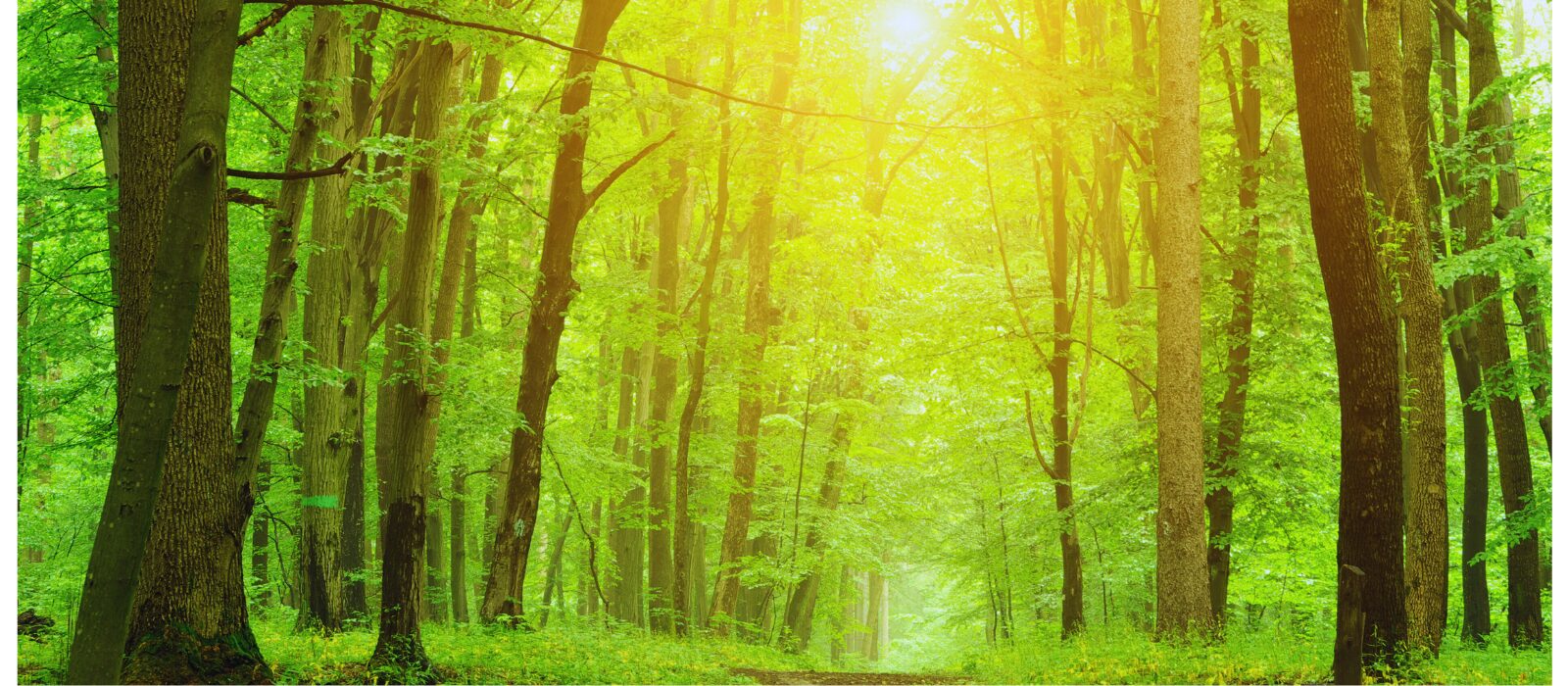「私を生き直す」− 宗教二世としての育ち、自己否定からの回復の物語 −
親子のすれ違い、傷つき、思い通りにかない現実、抑圧、偏見、差別、病、障害、喪失体験、孤立・・・
誰にでも、人生にはいろんなことが起こります。
私は、いわゆる世間で言われる「宗教二世」ですが、その呼び名自体に辛く感じたことも。
誰も悪者にしたくない、そんな気持ちも起こりました。
そして、同じ思いを抱えた様々な方の手記や物語に何度も励まされてきました。
ここに書いた物語は、私だけの特別のものではないかもしれません。
同じような経験をしてこられた方や、今悩みや苦しみの渦中にいる方に、
少しでも何か参考になることがあればとの願いを込めて。
信仰家庭に生まれて
熱心な宗教の信者の両親の元に生まれた私は、生まれて間もなく入信しました。
両親は生活の中心が信仰で、教団の活動が優先される日々。

家で靴を脱ぐのは当たり前、それと同じように、
「教団の教えを大切にすること」「指導者に忠誠心を持つこと」は、
ごく自然な日常の一部として、深く生活の中に組み込まれていました。
両親にとっての生きがいであり誇りである信仰を踏み躙るような態度や言葉は、
絶対に超えてはならない一線であることを、幼い頃から肌で感じ取っていました。
教団は、家族のような一体感の中で、大人に出会えば、
どんなときも皆温かく迎え入れてくれ、励ましてくれたり褒めてくれたりしました。
まるで教団の子どものように、壮大な夢物語の中で、
割り当てられた役割を演じ続けて生きていたようなところも
あったのかもしれません。
子どもの頃は、物質的には何不自由のない暮らしで、
苦手なことや嫌なこともあるけれども、
毎日は楽しいとも感じ、両親を慕ってもいましたし、誇りにも思っていました。
学校では、先生から気に入られるような良い子でもあり、
そんな自分を両親は喜んでくれ、可愛がってくれていました。
けれども、今振り返れば、どこかでずっと感じていました。
「本当の私を誰からも見られていない」
「ずっと見過ごされ続けている」
「誰からも知られていない」
言葉にできない不安感、
外の世界に対する漠然とした恐怖のようなものが、
心の奥に静かに潜んでいたのだと思います。
反発心が芽生えるも、自ら抑圧の道へ
思春期になると、信仰や教団の活動への反発を態度で示したり、
母親に対する不満や怒りをぶつけることがありました。
けれど、いつも疲れて苦労している母親の姿を目の前に、
私が母親を支えなければという思いとともに、
「私が母を苦しめている」と
反発心を持つ自分への罪悪感も強めていったのです。
この両親の世界、信仰の世界から抜け出したいという気持ちすらも持つこともできない、
口にも出せない、
「私は逃れられない」「変えられない」
そんな、深い諦めの気持ちや無力感が、私の中にいつしか静かに根付いていきました。

ただ周囲になんとなく合わせて過ごし、
自分の感情が認められず、
自分で考える、選択するということを避けるようになっていきました。
自分のあり方に、どこかしら違和感や不安を感じながらも、
自分ではどうすることもできず、
気づかないふりもしていたのだと思います。
そこに光を差してくれたものも、教団でした。
教団の指導者の本を読むと、そこには理想的な世界が描かれ、
美しく魅力的な言葉に触れ、生きる希望が湧いてくるように感じました。
そのような世界を作る一員に自分もなれば、
何かを達成でき、自分の価値を感じられ、
特別な何者かになることができる、
自分への嫌悪感を払拭していける気がしたのです。
そして、教団の価値観や指導者の語る世界観に心を寄せるようになっていきました。
けれど、気づけば、
少しは感じていた教団への些細な違和感や疑問、教義を探求したいという思いも、
忙しさの中でいつしか埋没していき、
「考える」ことをやめていっていた自分がいました。
私が頑張れば、両親が教団の中で認められる、
それが、自分にとっての喜びにもなっていたのかもしれません。
「誰かに認めてほしい」で、とにかく頑張り続け、
「なにかを達成しないと」「このままではいけない」で、
結果を求めて限界までがむしゃらに動き続ける、
そうやって、心の余白を失っていきました。
それで達成できたこともありましたが、
身体的不調も抱えるようになっていったのです。
「両親の信じる世界を離れて、自分の足で立つのが怖い」
「自分で決めることへの責任を負うことが不安」
そんな思いが、心の奥底にあったのだと、
今では思います。
子育てで浮き彫りになった、閉じ込められていた心
30代で結婚し、出産しましたが、
そこからが本当の意味での苦しさの始まりだったのかもしれません。
子育てで初めて知った子どもへの愛しさ。
けれど、同時に、「私はこんな風に愛された記憶がない」という悲しみも一気に溢れました。
子ども向けアニメの「生まれてきてくれてありがとう」の言葉に、
ふと涙が溢れたことを今でも覚えています。
そして、夫婦関係の行き詰まり、身体の不調・・・
信仰を子どもに受け継がせることは、「本当によいことなのだろうか」
という漠然とした不安も起こるように。
カウンセラーを職業にしていた私でさえも、
勇気のいる一歩でしたが、対話での心理療法を受け始めました。
信仰についても取り上げられましたが、
信仰は、私にとって、空気と同じように、当たり前に心身に刻まれているもの。
「脱会」の二文字を想像しただけで、震え上がるような恐怖を感じた自分に、驚きもしました。
そこから、自分がいかに強く縛られていたのかに気づき始めていったのです。
憲法の「信教の自由」は頭では知っていましたが、
自分には当てはまらないものと思っていました。
自分にとっての幸せとは何か、自分が何を求めているのか、
それを自分の言葉で語れないと気づいた時、
「私は私を生きていなかった」ことも痛感していきました。
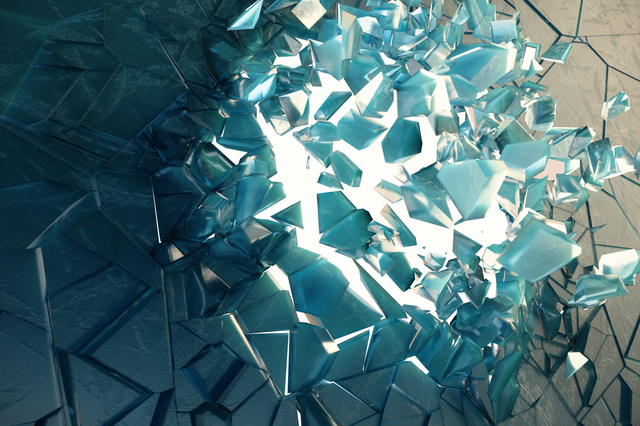
自分がこれから先に向かおうとする今の自分にはもう合わない
と感じられるものであっても、
これまで大切にしてきたものを手放したくない、否定したくないと思う、
そんな思いも溢れました。
私は、教団で多くの人々と触れ合い、世話になり、励ましてくれた友人もいました。
私が教団から離れることで、「恩知らず」になってしまうことの、
怖さと後ろめたさも溢れました。
「自己の再建」ありのままの自分と出会う旅路
その後、身体の不調も大きかった私は、
自然と、「身体そのものに働きかけるセラピー」を求めるようになっていきました。
そして、出会ったのが、身体感覚も扱うソマティック(身体志向)心理学の手法によるセラピーでした。
セラピスト達との出会いの中で、「新たな自己の再建の旅」が始まりました。
対話による心理療法では、私は、質問や疑問を投げかけられたとき、
言葉でセラピストに自分の思いを伝えるということが難しかったり、
思考ばかりが先走ってしまい、固まってしまうも多くありました。
ソマティックなセラピーでは、
ゆったりと「安心できる身体の感覚」に注意を向けることから始まります。
セラピストともに、丁寧に安心感を築き、味わいながら、
そこに一緒にセラピストに寄り添ってもらいます。
自身の感覚に従っていくことで、思いもよらない言葉やイメージや感情が湧き起こり、
それを自然と言葉にすることができました。
それは、温かく抱きしめられるような、深い充足感を伴う経験でした。
「全てを失った」と感じたとき、私を支えてくれたのは、他でもない
「生きている」と感じられる身体の感覚でした。
身体の中に確かにある、微細な動き、エネルギー、実感、感情、
そのひとつひとつに静かに気づき、言葉にすることで、
私は再び「自分自身」と出会い直すことができました。
このプロセスは、決して一人では向き合えなかったと思います。
身体で感じる安心という足場を少しずつ築いていくことで、
セラピストと一緒に、怒りや寂しさといったネガティブな感情についても
怖がらずに寄り添い、感じ、そのままに受け止めていきました。
一滴一滴の滴が、やがて流れを作るように、
何かを強引に変えるのではなく、どの感情もどの経験も、
自分の一部として丁寧に認めていく。
まるで、一枚の布の中のどの糸も無理に引き抜くことなく、
すべてを「私」という存在の一部として編み直していくようなプロセス。
その積み重ねのなかで、私はようやく、
暖かく優しい眼差しで、
自分の過去や現在、そして感情と
向き合うことができるようになっていったのです。

次第に、自分との向き合い方の変化から、日常生活で起こる負の感情や苦痛も、
圧倒されるのではなく、穏やかに向き合えるようになりました。
家族との関係も以前よりずいぶん楽になり、
より複雑な感情も、無理に決めつけたりせずに、
ただ「そこにあるもの」として、
心に置いておくことができるようになっていきました。
以前の私は、知らず知らずに白か黒か、正しいかそうでないか、
の両極端の判断をしていたことにも気づきました。
「正しさ」に縛られて、直感や感情に目が向けられなかった。
頭で、何が正しいかを判断するということだけに捉われず、
自分の感覚や感情と対話しながら、それを信じるようになりました。
そして、頭で考えすぎずに、必要でないものは自然と手放せる、
そんな感覚が少しずつわかるようになっていきました。
次第に、心の中の嵐が止み、しっかりと現実に自分の足で立っている感覚が
掴めるようになっていきました。
人にはそれぞれの感覚に即した、それぞれの価値観や選択や生き方があり、
どれも尊重されてもいいの。
「私は私であっていい」
「私を大切にしていい」
「どんな感情も心に置いていい」
そう感じられる余裕が、心の中に育ってきたように思います。
今の私は、特定の対象物に祈るわけではありません。
けれど、祈り、願い、そうしたものは私の心にあり続けています。
かつては、「感謝したくても、できない」と恨みや怒りと罪悪感が絡み合い、
胸の奥に重たいモヤモヤをずっと抱えていました。
でも今は、ふとした瞬間に、自然や家族、周りの人々、社会への感謝の気持ちが
自然と湧き起こることがあります。
そうすると、人との関わりも無理に頑張らなくてよくなりました。
心身の不調や痛みとも、戦わずに、優しく対話するようになりました。
自分とつながること、
その積み重ねが、日々の私の暮らしと心を、静かに、確実に変えていきました。
今、私が届けたいもの
私は、長い間、対話によるカウンセリングや心理療法を行い、
クライエントさんと共にたくさんの感動的な体験も分かち合いましたが、
行き詰まりや限界も感じてきていました。
話すことだけでは、届かない部分がある、
そう感じることが何度もありました。
そんな中で出会ったのが、身体志向のアプローチでした。
これは、私の回復と成長にとっても、そして、クライエントさんとのセッションにおいても、
とても有効な手がかりとなってくれました。
言葉だけでは、本当に伝えたいことにたどりつかないことがある、
過去を話せば話すほどに、苦しさや傷が溢れ出てしまうことがあります。
無理に語らなくてもいい、
全部を思い出さなくてもいい、
問題を問題視しすぎなくてもいい。
心と体の「器(コンテナ)」を整えていくことで、
「困難を消化し、未来に向かっていく力」が、
人には備わっていると、今では確信しています。
私たちは、生まれる環境や自身の特性を自分の意志で選択することはできません。
現実社会という大きな渦の中で、そして閉鎖された家庭の空間や親子関係において、
知らず知らずのうちに様々な価値観や信念を持つに至り、
心身ががんじがらめになってしまっていることがあります。
どんな人の中にも、「その人らしい心の声」が息づいています。
そして、誰もが、その人らしい心の声を、
誰かに見守れらながら、耳を澄まし、大切にされる体験。
それこそが、人生を再び主体的に歩み直していく力になるのだと思います。
心の不思議さ、強さ、力、自由さ、奥深さ。
私自身も、それに向き合い、
そして、向き合ってもらう中で、癒されてきました。
そして、この経験を生かして、
かけがえのない人生を、あなたらしい感覚を大切にしながら、
主体的に生き抜いていけるようなお手伝いをしたいと思っています。

どうかあなたも、あなたの心にある小さな声に耳を傾けてくれる誰かと出会えますように。
きっとあなたも大丈夫。